真空低温調理をするためには、しっかりとした空気抜きが必須です。
脱気不足になると、袋に残った気泡が加熱の邪魔して、加熱ムラの原因になったり、
袋がしっかりと湯煎に沈まなくなってしまいます。
真空低温調理を始めるなら、空気抜きは必須の技術です。
とは言っても、空気抜きはどれも非常に簡単にできてしまいます。
真空低温調理以外にも、食材の保存の際に活用することで、鮮度が長持ちしたり、
漬物や下ごしらえにも応用できたりと、覚えておいて損のない技術です。
低温調理に使える空気抜きの3つの方法
では低温調理で良く使う、3種類の空気抜きを方法をご紹介します。
- 浸水法。
- ストロー脱気法。
- テーブルエッジ法。
詳しく紹介します。
浸水法
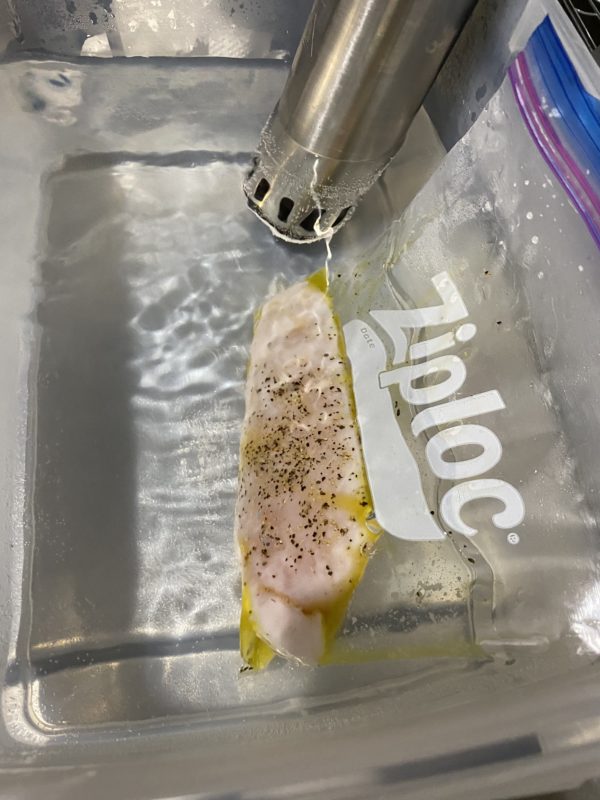 非常に簡単な方法なので、初めてでも簡単に出来ます。
非常に簡単な方法なので、初めてでも簡単に出来ます。
やり方は、
- ジップロックなどのジッパー付きの袋に食材を入れる。
- 最初にジッパーを8割くらいまで閉じておく。
- そのまま低温調理の湯煎に沈める、そうすると水圧で勝手に空気が抜けていく。
- 食材が浮いてくるときは、菜箸やトングを使って沈める。
- 袋の一番上まで浸水出来たら、ジッパーを完全に閉じて完成。(袋の中に水が入らないように注意する)
空気抜きに迷ったらとりあえず浸水法で大丈夫です。
ストロー脱気法
野菜などの空気が残りやすい食材は、浸水法では難しいです。
不可能ではありませんが、浮力が強く、無理に沈めようとすると最悪袋が破けてしまいます。
そこでおすすめしたいのが、ストロー脱気法。
- ジップロックなどのジッパー付きの袋に食材を入れる。
- ジッパーにストローを挟み、ジッパーをギリギリまで閉じる。
- ジップロックの中の空気を吸い込む。(結構大変なので頑張って吸ってください)
- 完全に脱気は難しいが、ある程度は脱気出来る。
ストロー脱気は、主に凸凹が多い野菜などの空気抜きに適しています。
テーブルエッジ法
真空低温調理では、液体が多い煮物系で使います。
- ジップロックなどのジッパー付きの袋に食材を入れる。
- テーブルや台などの縁に液体のギリギリのところをあわせます。
- そのまま引っ張って空気を抜きます。
- 空気を抜き切ったらジッパーを閉めます。
真空低温調理以外だと、調味料に食材を漬け込みたいときなどに応用できます。
効率よく真空したいなら真空パックという手段も
真空パック機の活用
真空パック機を活用できれば、真空作業は一気に楽になります。
空気ができやすいブロッコリーなどもほぼ完璧に脱気することが出来ます。
大量に真空しておくことで、その都度低温調理器で加熱するだけで調理が出来てしまいます。
更に、コストコなどの業務用サイズの食材の保存にも適しています。
真空パック機のデメリット
ただ、真空パック機にはデメリットもあります。
1つ目は、真空パック機自体が高価なもので、初期費用がかかることで、
2つ目は、その都度掃除のメンテナンスが必要なことです。
真空パック機を使いこなせるかは、いかに活用し切れるかにかかります。
一人暮らしには不要
私自身も真空パック機を購入しましたが、結果としてはメルカリで売りました。

真空性能に関しては文句なしでしたが、一人暮らしのキッチンは場所が狭く、コンセントも少ないです。
パック詰めの作業がはかどらず、掃除も面倒になり、結局ジップロックで浸水法をするのが一番楽で効率的でした。
低温調理に使える空気抜きのまとめ
よく使う空気抜きの方法は以下の3種で、
- 浸水法。
- ストロー脱気法。
- テーブルエッジ法。
ちなみに、野菜でもニンジンやジャガイモは浸水法の方がやりやすいです。
食材の形状をみて、なるべくなら浸水法で空気抜きするのが一番やりやすいです。
空気抜きは、真空低温調理以外にも下ごしらえや食材の保存にもつかえるので、
ぜひ応用して使ってみてください。





